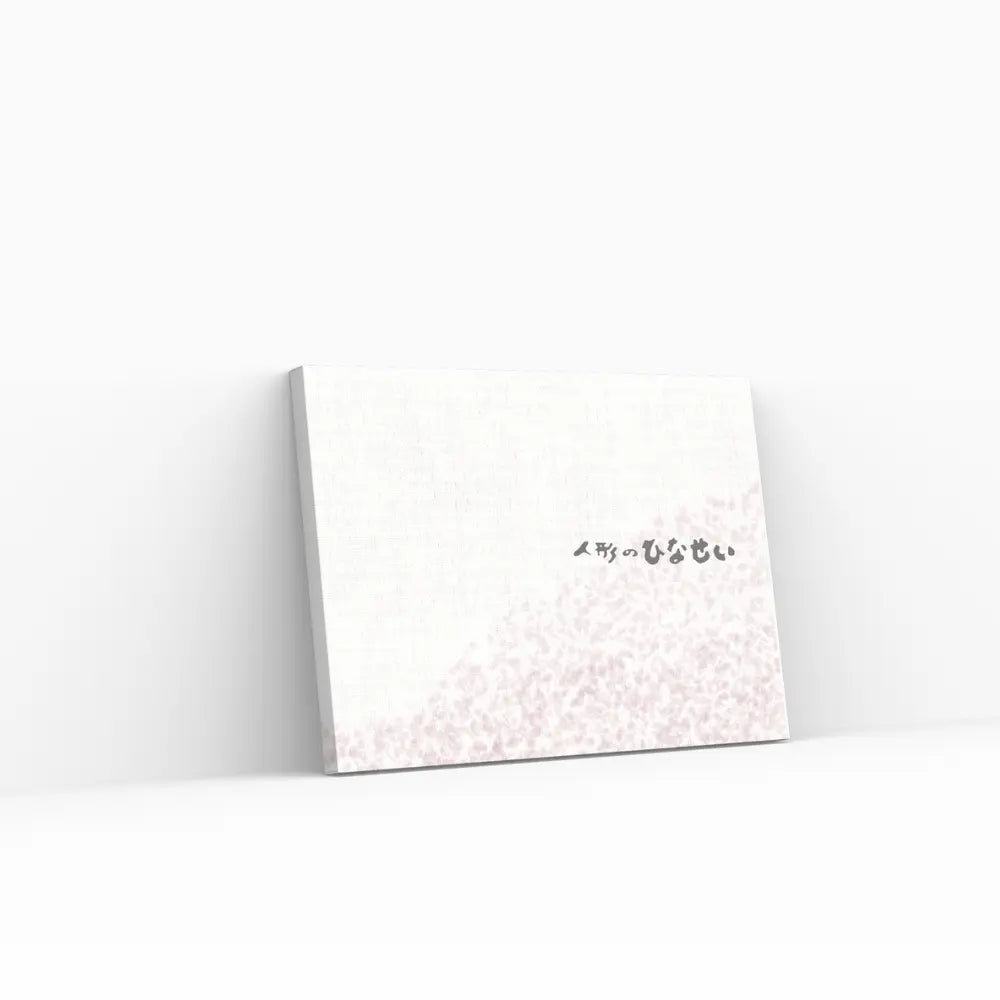9月9日の重陽の節句とは?意味、由来、伝統行事
ここでは日本の古くからある伝統行事の一つ、
五節句の一つの月9日の重陽(ちょうよう)の節句について解説します。

ちなみに、有名な他の5節句は
「お正月」、「ひな祭り」、「こどもの日」が該当します。
専門的な言い方を知りたい方は、
「日本の伝統文化の五節句について詳しく知る 」をご覧ください。
ご参考になれば幸いです。
---- 目次 ----
以下をクリックするとジャンプします
8. 日本の伝統行事を知ろう
〜節分、お盆、正月、七夕の紹介〜
9. 菊の被せ綿とは?
〜重陽の節句にまつわる風習とその意味〜
11. 秋の年中行事と重陽の節句
〜秋祭りや敬老の日との関連性〜

重陽の節句とは?読み方と意味、由来を簡単解説
重陽の節句とは 9月9日に行われる、長寿や健康を祈る日本の伝統行事です。
重陽の節句(ちょうようのせっく)は、
日本の伝統行事で9月9日に行われます。
この日は「陽」の数である9が重なる日で、特に縁起が良いとされています。
古代中国から伝わったこの節句は、
菊の花を飾り、菊酒を飲むなどして健康や長寿を祈る行事です。
日本でも平安時代から行われ、現在でも一部で祝われています。
簡単に言うと、重陽の節句は家族や自分の健康を願う日です。
五節句 他の節句(人日、端午、七夕)との関係
五節句の一つ:
重陽の節句 他の節句(人日、端午、七夕)との関係も重要です。
重陽の節句は、
1月7日の人日、3月3日の上巳、
5月5日の端午、7月7日の七夕と並ぶ五節句の一つです。
これらの節句は季節の変わり目に健康や幸せを願うために行われます。
重陽の節句は特に長寿を祈る日として知られています。
五節句は、それぞれが異なる意味を持ち、
日本の文化や歴史に深く根付いています。

重陽の節句は<9月9日>に行う
9月9日に行われる伝統行事。
では重陽の節句で何をするの?
重陽の節句では、菊の花を飾り、
菊酒を飲んで健康や長寿を祈ります。
また、3月3日に飾ったひな人形を再び飾る「後の雛」という風習もあります。
これは、ひな人形をもう一度飾ることで家族の無病息災を願う行事です。
これらの風習は、日本の伝統的な生活に深く根付いており、
家族で簡単に取り入れることができます。
重陽の節句の日付の意味と歴史的背景
なぜ、9月9日なのかな?
重陽の節句 日付の意味と歴史的背景を解説します。
9月9日が重陽の節句に選ばれた理由は、
「陽」の数である奇数が重なるからです。
特に「9」は最も大きな陽数であり、
中国では古くから縁起が良いとされています。
この考え方が日本にも伝わり、
平安時代から9月9日に重陽の節句が祝われるようになりました。
この日は菊の花を使った行事が中心で、
健康や長寿を祈る意味があります。

後の雛とは?重陽の節句とひな人形の関係を解説
3月3日に飾ったひな人形を再び飾り、長寿を祈る風習です。
後の雛について・・・
後の雛(のちのひな)とは、
3月3日の桃の節句で飾ったひな人形を9月9日の重陽の節句に再び飾る風習です。
これは、ひな人形を風通し良くすることで長寿を願う意味があります。
元々は江戸時代に始まり、大人の健康を祈る行事として広まりました。
現代でも一部の地域で続いており、
ひな人形を再び飾ることで家族の健康を祈ることが目的です。
重陽の節句で祝う菊酒
作り方と健康祈願の意味
健康と長寿を祈るために飲まれるお酒について解説します。
重陽の節句で祝う菊酒
菊酒は、重陽の節句で飲まれる特別なお酒です。
菊の花を日本酒に漬け込み、その香りとともに邪気を払うと信じられています。
このお酒を飲むことで、健康と長寿を願う風習があります。
作り方は簡単で、菊の花を摘み取り、日本酒に浮かべるだけです。
重陽の節句には、家族で菊酒を楽しみながら、
健康を祈る時間を過ごしてみてください。
重陽の節句で長寿を願う
不老長寿の祈りと風習の意味
菊を使って長寿を祈る日本の伝統的な行事です。
重陽の節句で長寿を願う
重陽の節句は、不老長寿を願うための大切な行事です。
この日は、菊の花を飾り、菊酒を飲むことで、長寿や健康を祈ります。
また、菊に綿をかぶせ、その香りを吸収した綿で体を拭く
「菊の被せ綿」という風習もあります。
これらの伝統的な風習は、家族の健康を守るために行われ、
今でも一部の地域で大切にされています。

節分、お盆、正月、七夕の紹介
日本の伝統行事を知ろう
節分、お盆、正月、七夕について紹介します。
日本には、季節ごとにさまざまな伝統行事があります。
例えば、節分は2月に行われ、鬼を追い出し福を呼び込む行事です。
お盆は8月に先祖の霊を迎える期間で、家族でお墓参りをします。
正月は1月1日から始まり、家族や友人と新年を祝う大切な時期です。
そして、七夕は7月7日に、織姫と彦星の伝説を祝う行事です。
これらの行事は、日本の文化と伝統を深く理解するために大切なものです。
菊の被せ綿:
重陽の節句にまつわる風習とその意味
菊の被せ綿とは、重陽の節句で長寿を願うために行う風習です。
菊の被せ綿について・・・
菊の被せ綿(きくのきせわた)とは、
重陽の節句に行われる風習で、9月8日の夜に菊の花に綿をかぶせ、
翌朝にその綿で体を拭いて長寿を祈るものです。
この風習は、菊の香りを綿に移し、
その香りで邪気を払い、健康を保つと信じられていました。
平安時代には宮中で行われていたとされ、
現代でも一部でその伝統が続いています。
この風習は、家族の健康と長寿を願う大切な行事です。
現代の重陽の節句 簡単に
取り入れたい祝い方と行事
菊を飾り、家族で菊酒を楽しむ簡単な祝い方が推奨されています。
現代の重陽の節句では、伝統的な風習を簡単に取り入れて祝うことができます。
例えば、菊の花を家に飾ることや、
菊酒を用意して家族と一緒に飲むことが一般的です。
また、季節の花を使った簡単なアレンジメントや、
和菓子を楽しむこともおすすめです。
これらの方法は、忙しい現代人でも手軽に取り入れることができ、
家族で楽しい時間を過ごしながら、長寿や健康を祈ることができます。

秋の年中行事 秋祭りや敬老の日との関連性
秋の行事と重陽の節句
秋祭りや敬老の日が関連について解説します。
秋の年中行事と重陽の節句
秋の年中行事には、重陽の節句の他にも、
地域ごとの秋祭りや敬老の日があります。
秋祭りは、収穫に感謝し、豊作を祈るために行われる伝統的な行事です。
敬老の日は、9月に祝われ、高齢者の健康と長寿を願う日です。
これらの行事は、秋という季節に健康や
幸福を願うという共通のテーマがあります。
特に重陽の節句は、秋の始まりを告げる行事として、
家族で楽しむことができます。
まとめ
重陽の節句を通じて
伝統を学び、長寿を祈る
重陽の節句は、日本の伝統行事の一つで、
健康と長寿を祈るために行われます。
まとめ 日本の行事 重陽の節句
9月9日に行われる五節句の1つである重陽の節句は、
日本の伝統行事です。
この重陽の節句の意味や風習は
健康と長寿を祈るための目的を持った行事です。
具体的に行うこととしては
菊の花を飾って菊酒を飲むことで
この健康・長寿の願いが叶うという風習です。
また後の雛という風習もあります。
3月3日にひな祭りで雛人形を飾りますが、
この雛人形を再び9月9日に飾り
長寿を願うという意味も込められております。
このように日本の大切な伝統、風習、しきたりは、
実に心温まる風情の一つでもあります。

雛人形・結納の陣屋さんのブログ記事でも、
重陽の節句について紹介されています。
古くから伝わる風習を、次の世代にも伝えていきたいですね。