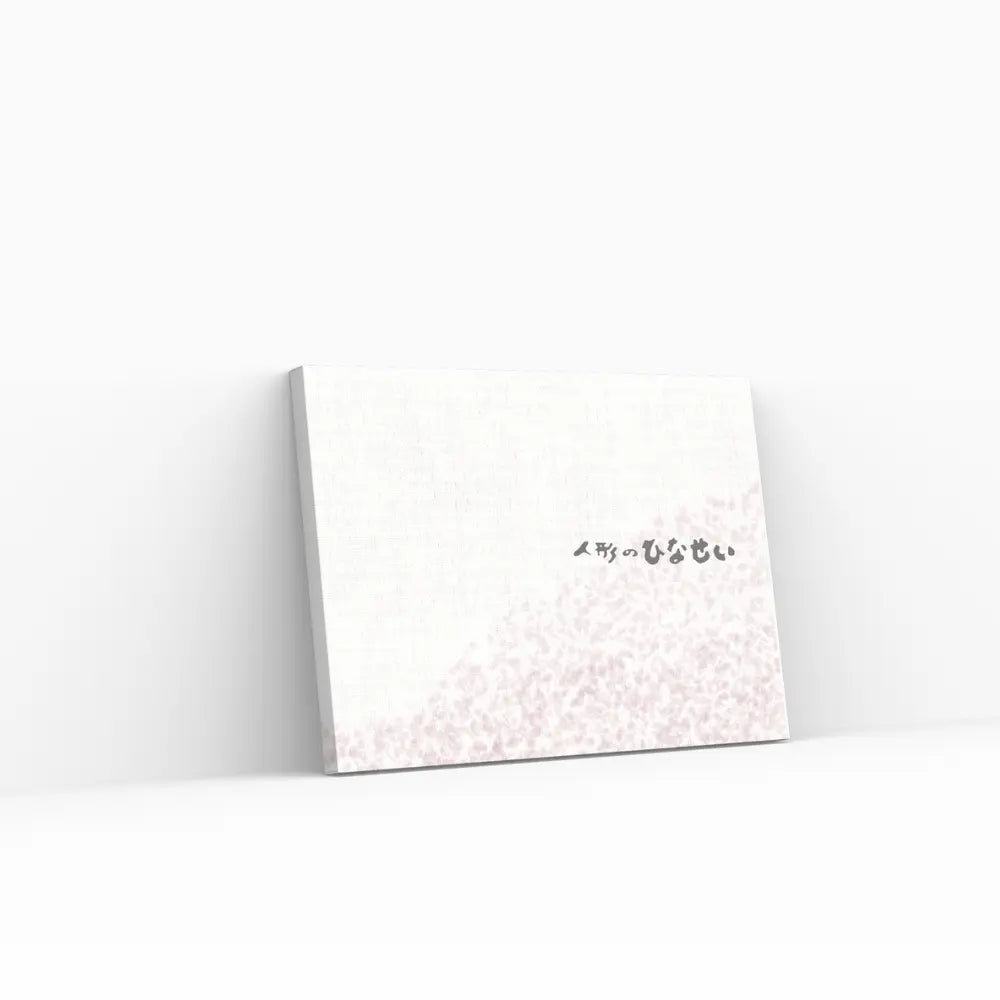雛人形工房で作り上げるモノ【ひな人形のひなせい】
雛人形業界唯一の古民家調の雛人形セットは、ここから始まりました。
私は日本が好き、古い町並みが好き。
ひな祭りは日本古来のイベントです。
ひなせいの目指すところ
西洋風に街が変わってくるこの時代、日本の街並みや日本家屋がどんどん洋風化していっています。それも、全世界同じような街並みの近代化です。
「日本らしさを感じるひな祭りをしたい」
「日本のひな祭りには、どのような味付けができるのか?」
そう考えていました。

そんな頃にあった一人のリクエスト
日本らしさあふれる街並み。
こんな街並みを見ると、昔懐かしい古き良き時代を感じます。
私が幼少だった時を思い出すと、島田のおじいちゃんの家に遊びに行った時のことが蘇ります。
薄暗い家の中で、家族みんなで過ごしていました。
そこには囲炉裏があって、薪がパキパキと音を立てて燃えていました。
暖かく感じたこの家の中での想い出、懐かしさ。
「私が最愛の娘にひな祭りをしてあげるなら、こんな感じのひな祭りをしたい」
そんな一人の女性からのリクエストが、私たちの物作り工房のスタートでした。
京都のような街並みの雰囲気を目指して
「京都の古い街並みのような雛人形が提供できないだろうか?」
ひなせい工房という雛人形を作る集団は、まるで京都のような街並みの雰囲気を目指しました。
しかし、雛人形業界の今までの素材では、この味付けができませんでした。
「どのようにすれば、雛人形にこのテイストが出せるのだろうか?」
いくら既存の素材を加工しても、どう努力しても失敗ばかりでした。
そこで、限りなく天然の素材からの加工に変更していきました。
どの材料を使うのか、どの素材でどう味付けさせていくのか。
雛人形工房での試行錯誤の繰り返しの日々が続きました。

京都で見つけた答え
たまたま別件で京都を訪れた時、神社の修復を見て気付いたのです。
そこには天然の杉の木を使い、木の肌が新品の白木の状態を加工していました。
木の目のぬくもり。
「そうか!材料を杉にして酸化を速めればいいのだ」
この木の目を最大に生かす選別、そして囲炉裏で燃え出る「すす」を利用する。
こういう工程を経ることによって、古民家調の雰囲気を醸し出せたのです。
そこには限りなく自然の材を自然な形で使う、という考えがありました。
そして複数年かけて辿り着いたのが、国産の杉の材をふんだんに使い作り込み、良い所だけを選び取り作りあげている古民家調の素材です。
日本らしさを追求して辿り着いた古民家調の雛人形
素材は天然の杉の材。
中には樹齢30年を超すものもあります。
暖かい木のぬくもりを感じる木の目が特徴です。
こんな味付けの人気な雛人形の屏風と飾り台。
確かに木の素材までこだわり、特殊加工を施して作ると、さすがに工房での生産数量は限られてしまいます。
まずは気に入ってくれる人だけでいい。大量生産はしません。
私たち雛人形工房では、決して大量生産・大量販売を求めてはいません。
少量でもいいので、納得して購入してくれる方に、こだわりのお雛様を届けたい。
そう願ってやってきました。
当初は、なかなか世の中に認められずにいましたが、今では複数年の積み重ねが、当社の技術や独自性として認められるようになってきました。
大井川の恵みを受けた杉材
大井川という大量の水量がある近隣の山々の杉材を選びました。
この地域は、お茶で有名なトップブランド川根茶が取れるところです。
木々の成長を後押しする大量の湿気を含んだ大気が、木々の成長を促します。
このような地域で育った杉を、さらに味付け加工して雛人形の屏風・飾り台を作り上げているのです。
輸入の素材ではなく、世間で流通しているプリントの材料を使わず、本物の材を使う。
木のぬくもり感を惜しげもなく引き出している古民家調の雛人形なのです。
決して多くを作らず良質なものだけを作る考えで、この古民家調の雛人形の屏風・台はできあがっています。
スタッフの成長に感謝
今は、立場上あまり作業の現場には口を出さなくなりました。
スタッフに任せ、信頼をおき各自の責任で仕事をしてもらうようにしました。
実際、私も他の業務が多くなり社長としての役割の仕事に専念させてもらっています。
そのようなことができるのも、スタッフの成長に感謝しているからです。

共に製作、企画
正直、新しい商品を世の中に送り出す瞬間は非常に疲れます。
非常に知恵を使います。
ですが、企画が世の中に認められ仕事ができることの喜びは、もっと嬉しいものがあります。
「あのご家族に満足を与えることができた」
そんな瞬間にお会いできる喜び。
こんな気持ちを忘れずに、コツコツと切磋琢磨しながら雛人形工房での物作りに励んでいます。